がん検診は何歳から受ける?受けるべき人の特徴を徹底解説

がん検診のお知らせが市区町村などの自治体から届いていても、「自分はまだ大丈夫」だと考え受診を先延ばしにしていませんか?
がんは年齢に関係なく発症する可能性があり、早期発見・早期治療が何よりも重要です。
この記事では、がん検診を受けるべき人の年齢や特徴、各種がん検診の内容などについてわかりやすく解説します。がん検診を受けることを検討している方は、ぜひ最後までお読みください。
がん検診は何歳から受診する?
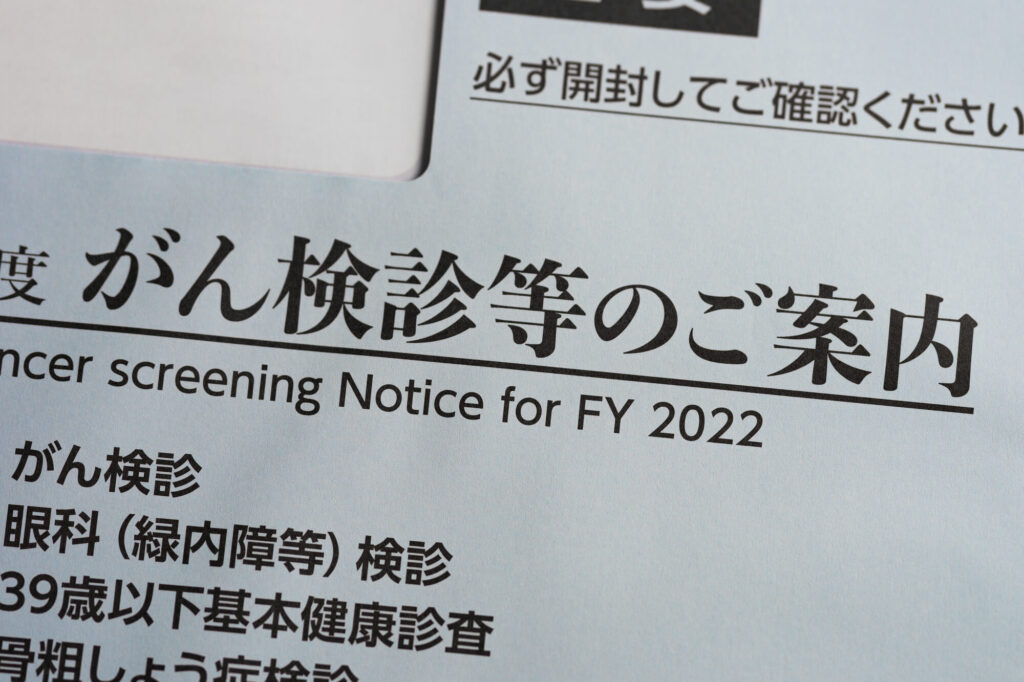
がん検診は、女性は20代、男性は40代から受けるべきとされています。
女性の場合、子宮頸がん検診が20歳以上、乳がん検診が40歳以上の方に推奨されます。男性の場合、40歳を過ぎたら大腸がん検診・肺がん検診が推奨されます。
これは、統計として罹患しやすいがんの種類や年齢に特定の傾向があるためです。
がん検診は、がんを早期に発見して治療につなげるために欠かせない重要な手段です。そのなかでも、国が死亡率を減らす手段として特に推奨しているのは、子宮頸がん・乳がん・肺がん・大腸がん・胃がん5種類の検診です。
がん検診を受けるべき人の特徴

がん検診を受けるべき人の特徴として、年齢以外にも注意すべき条件があります。以下に当てはまる人は、積極的にがん検診を受診すると良いでしょう。
- がんの家族歴がある人
- 喫煙習慣のある人
- 生活習慣の乱れがある人
- 性行為の経験がある女性
これらについて詳しく見ていきましょう。
がんの家族歴がある人
両親や祖父母、兄弟・姉妹などの近親者にがんの既往がある場合、自身もがんを発症するリスクが高くなることがあります。
特に乳がんや大腸がん、卵巣がんなどは遺伝的要因での発症が多いことが知られています。また、がん患者の5~10%は、生まれつきの遺伝子の変異を持っていることもわかっています。
がんの家族歴がある人は、できるだけ早い段階でがん検診を検討しましょう。
遺伝しやすいがんの種類については以下の記事でも解説していますので、ぜひご覧ください。
>>遺伝しやすいがんの種類や検査方法を解説
喫煙習慣のある人
日頃から喫煙習慣のある人も、健康維持のためにがん検診を受けることが大切です。
タバコは多くのがんのリスク因子として知られており、特に肺がんとの関連が深いです。喫煙者は非喫煙者に比べて、がんの発症リスクが高まります。
さらに、受動喫煙でもがんのリスクが高くなるため、自分が喫煙しなくても喫煙環境に長くいる人は注意が必要です。
がん検診は、このようなリスクを抱える人のがんを早期に発見し、治療につなげるために有効な手段です。
生活習慣の乱れがある人
過度な飲酒や脂質・糖質に偏った食生活、慢性的な運動不足、過労による睡眠不足などの不健康な生活習慣は、がんのリスクを高める可能性があります。
特に、過度な飲酒は食道がんや肝臓がん、大腸がんなどと深く関係しているといわれています。
生活習慣が乱れている自覚があったり、周りから指摘されたりする人もがん検診を検討しましょう。
性行為の経験がある女性
性行為の経験がある女性は、子宮頸がんのリスクを考慮して、子宮頸がん検診を受けるべきとされています。
子宮頸がんの主な原因は、ヒトパピローマウイルス(HPV)というウイルスへの感染です。HPVは性行為を通じて感染し、数年から十数年の期間を経てがん化する可能性があります。HPV以外の原因で子宮頸がんに罹患する可能性もわずかにありますが、性行為の経験がない女性が感染するのはまれです。
子宮頸がんの初期は自覚症状がほとんどないため、定期的ながん検診での早期発見が重要です。そのため、性行為の経験があるすべての女性に、子宮頸がん検診の受診が推奨されています。
がん検診を受けないほうがいいと言われる理由

ここまでお話ししたように、がん検診は早期発見・早期治療の手段として推奨されていますが、一方で「がん検診は受けないほうがいい」との意見も聞かれ、それなら受けなくても良いかと思ってしまう方もいるかもしれません。
結論として、がん検診は定期的に受診すべきですが、受けないほうがいいと言われる理由としては以下が考えられます。
- 偽陽性が起こる可能性がある
- 過剰診断が起こる可能性がある
- 偶発症のリスクがある
偽陽性が起こる可能性がある
がん検診では、がんがないのに“要精密検査”とされる「偽陽性」が発生する可能性があります。
偽陽性となった場合、本来必要のない精密検査を受けることとなり、金銭的負担や不安による精神的ストレスが発生します。そのことから、がん検診は受けないほうがいいと考える人がいるものと予想されます。
過剰診断が起こる可能性がある
過剰診断とは、放置されても健康や生命に影響を与えない病変までがん検診で検出してしまうことです。
病変があったとしても、そのすべてが命に影響を及ぼす訳ではありません。病変の状態や年齢などにより、一生涯において症状が現れないケースもあるのです。
このように、治療の必要がない病変ががんと診断されることで、手術や放射線治療、抗がん剤治療など不要な治療を受けることになります。
過剰診断が不安であるために、がん検診は受けないほうがいいと感じる方もいるのでしょう。
偶発症のリスクがある
がん検診では、検査そのものに伴う偶発症(予想外に発生する有害事象や症状)のリスクもゼロではありません。
胃カメラなどの内視鏡検査ではまれに出血や穿孔が起こることがあり、バリウム検査ではバリウムの誤嚥や便秘が問題になることもあります。また、CT検査やマンモグラフィなどの放射線を使用する検査では、わずかに被爆するリスクもあります。
偶発症が発生する可能性は非常に低く、検診を受けるメリットのほうが大きいものではありますが、リスクを回避するためにがん検診は受けないほうがいいと考える方もいることが予想できます。
がん検診(疾患別)の推奨年齢

がん検診は、がんの種類ごとに推奨される開始年齢や受診頻度が異なります。これは、がんの発症年齢や進行の特徴に基づいて国が科学的根拠に基づき定めたものです。
年齢に応じて定期的にがん検診を受けることで、がんの早期発見と早期治療につながり、死亡リスクを下げられる可能性が高まります。ここでは、主要ながん検診の推奨年齢や受診頻度について見ていきましょう。
子宮頸がん検診は20歳以上から
子宮頸がん検診は、20歳以上の女性を対象に2年に1回受けることが推奨されています。検査内容は、問診、視診、子宮頸部の細胞診、内診などです。
自治体によっては、30歳以上を対象にHPV検査単独法を導入している場合もあります。
子宮頸がんは、若い世代でも発症するリスクがあるため、性行為の経験がある女性は特に定期的な受診が勧められています。
乳がん検診は40歳以上から
乳がん検診は40歳以上の女性を対象に、2年に1回受診することが推奨されています。
検査は問診のほか、マンモグラフィという乳房のX線検査が中心です。
乳がんは閉経前後の女性に多くみられ、早期発見が治療成績に大きく影響するため、定期的な検診が重要です。
肺がん検診は40歳以上から
肺がん検診は40歳以上の男女を対象に、年に1回の受診が推奨されています。
検査内容は問診と胸部X線撮影が基本ですが、喫煙歴のある50歳以上の方で喫煙指数(1日の本数×年数)が600以上の場合には、痰を用いた喀痰細胞診も併用されます。
肺がんは喫煙との関連が深いため、喫煙者は特に注意が必要です。
大腸がん検診40歳以上から
大腸がん検診は40歳以上の男女を対象に、年1回受診することが勧められています。
検査は問診と便潜血検査で、比較的負担の少ない方法でがんの兆候を探ることが可能です。
定期的な便潜血検査によって、大腸がんによる死亡率が下がることが報告されています。
胃がん検診50歳以上から
胃がん検診の推奨年齢は50歳以上で、2年に1回の受診が基本です。
検査方法には、問診に加えて胃部X線検査(バリウム検査)または胃内視鏡検査(胃カメラ)があります。内視鏡検査は直接観察ができるため、より精度の高い検査とされています。
胃がんは50代以降から年齢とともに発症リスクが上がるため、定期的ながん検診の受診が望ましいです。
参考:厚生労働省ホームページ「日本の健診(検診)制度の概要」
がん検診の費用

国が推奨している子宮頸がん・乳がん・肺がん・大腸がん・胃がんの5つのがん検診は、各自治体から費用の一部または全額の補助があるため、自己負担額は0円から3,000円程度で受けられます。
子宮頸がんや乳がん検診などは、年齢や条件によって無料になるケースもあります。
胃がん検診で胃内視鏡検査を選んだ場合は、検査機器や処置の内容によって2,500円以上の自己負担が発生することもあり、自治体や施設によって費用に差があるため、事前の確認が必要です。
定期的にがん検診を受けるうえで、費用面での負担は少なく済むようになっています。
参考:厚生労働省ホームページ「令和3年度 市区町村におけるがん検診の実施状況調査 全国集計」
がん検診と並行して人間ドックの受診も

がんの早期発見にはがん検診が欠かせませんが、健康状態を総合的にチェックするには、人間ドックの受診も併せて検討することが重要です。
国が推奨するがん検診は上述した5つのがんに限定されており、それ以外のがんや疾患に対する検査は含まれていないのが一般的です。
一方で人間ドックでは、全身のがんに対応する幅広い検査項目が用意されており、自身の年齢や性別、家族歴、生活習慣などに応じて、必要なオプション検査も追加できます。
さらに、人間ドックはがんの有無だけでなく、脳疾患や心疾患、糖尿病・高血圧・脂質異常症など生活習慣病の兆候も確認できるため、将来の重大な疾患の予防や健康寿命の延伸につながる可能性があります。
特に自覚症状が出にくい病気に対しては、定期的な検査が重要です。年に1回の人間ドックを受けることで、異常の早期発見・対応が可能となり、治療の選択肢や予後にも大きく影響するでしょう。
人間ドックの費用は保険適用外となるため自己負担となりますが、企業によっては福利厚生で費用の補助が出たり、自治体によっては助成制度が設けていたりするケースもあるため、確認してみましょう。
自身の健康状態を守るためには、がん検診だけでなく、人間ドックを定期的に受ける習慣を持つことも理想です。
人間ドックによるがんの検査については、以下の記事でも解説していますのでぜひお読みください。
>>人間ドックとがん検診の違いとは?検査項目や費用を比較
>>全身がん検査をするには?費用や検査方法を解説
まとめ

この記事ではがん検診を受診すべき年齢や受けるべき人の特徴、疾患別のがん検診の内容などについて解説しました。
がん検診は、がんの早期発見・早期治療に欠かせない重要な手段です。国が推奨する子宮頸がん・乳がん・肺がん・大腸がん・胃がんの5種類は、それぞれの発症リスクに応じた年齢からの受診が推奨されています。
がんの家族歴がある人や喫煙習慣のある人、生活習慣が乱れている人、性行為の経験がある女性などは、推奨される年齢に満たない場合でも積極的にがん検診を受けることが望まれます。
また、がん検診だけでなく人間ドックを併せて受けることで、他のがんや生活習慣病のリスクにも対応でき、健康寿命の延伸にもつながる可能性があります。
自身の年齢やリスクに合った検査を定期的に受診し、健康を守る第一歩を踏み出しましょう。
セントラルクリニック世田谷では、PET-CTやMRIなど高精度の医療機器を導入し、質の高い人間ドックを提供しております。
「総合がんPETドック」をはじめ、全身のがんの早期発見に特化したコースも準備しております。
人間ドックの受診先をお探しの方は、お気軽にセントラルクリニック世田谷までご相談ください。

